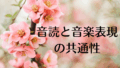こんにちは!入間市で子ども向けピアノ教室をしております、いいじまです^^
今日は、ピアノの練習を習慣化する方法についてお話ししようと思います♪
練習しない≠練習出来ない
「うちの子、なかなか練習しなくて…」
子どものピアノ講師をしていると、保護者の方から様々なご相談をいただきますが、やはり一番多いのがこの”練習しない”問題です。
中学生くらいになると、もっと他のことに興味が出てきた、という場合もあるでしょうが、小学3~4年生くらいまでは、やりたくないからやらない、というより、そもそも一人で練習が出来ない、という場合が多いのではないでしょうか。
つまりお子さんが、
・練習の仕方がわからない(いつも最初から通して弾いてばかりで、つっかえつっかえ…)
・譜読みが出来ない(一音ずつ数えている、リズムがわからない)
という状態だと、せっかくピアノの前に座っても練習にならないのです。
以前こんなことがありました。
Aちゃんがレッスンを休んだワケ
その日はAちゃん(小3)のレッスン日でしたが、時間になってもやって来ません。心配しているとお母様からお電話が。
「先生すみません、Aが部屋から出て来ないんです…」
困り果てた様子のお母様に、何があったのか尋ねたところ、
「今週は私の仕事が忙しくて、全然練習を見てあげられなかったんです。学校から帰ったらピアノの練習をしておくように、Aに言ってはいたんですが、ほとんどやってなかったようで…。『全然出来てないから今日はレッスンに行かない!』と言って部屋に閉じこもってしまったんです。」と申し訳なさそうに教えてくださいました。
私はまず、「こちらこそ、お忙しい中いつも練習にお付き合いいただいて、本当にありがとうございます。」と日ごろの感謝を述べました。ご家庭の協力があってこそ、ピアノのレッスンは成り立つのです。その上で、
「練習がうまくいかないこともありますよね。そういう時は、ひと言メモでも書いて持たせていただければ、そのように対応しますから大丈夫ですよ。」とお話ししました。
Aちゃんも、恥ずかしさや後悔の気持ちでいっぱいだから、レッスンに行きたくない!となったのでしょう。落ち着いたら、
「もしまた今週みたいに練習がほとんど出来なかった時があっても、レッスンは休まないで来てくださいね。レッスンで先生と一緒に練習しましょう♪」と伝えてもらうようにお願いしました。
レッスンで心がけていること
今回のAちゃんのケースは、ちょうど発表会に向けて新しい曲の譜読みに取り掛かったところだったので、極端な例かもしれません。ですが、お母様のお仕事の都合ばかりでなく、ご家族が体調を崩してしまったなど、思うようにいかないことはよくありますよね。
ですから、ご家庭での練習において、お母様の見守りのご負担が少しでも軽くなるように、との思いを持ちながらレッスンしていますし、特に新しい曲に入る時は、楽譜への興味付けをしてから持ち帰ってもらうように、私は心がけています。
生徒さんの読譜力のレベルにもよりますが、まだまだ怪しいなぁという場合には、いきなり弾くのではなく、
・メロディーをドレミで歌ってみる
・メロディーのリズムを手で叩いてみる
というような方法で、新しい曲への導入を行うことがあります。
実際に弾いてみる、となると、さらに指づかいも気にしなければなりませんから、音とリズムを先に把握しておくことで、スムーズに鍵盤に移れるんです。
スタート時間を決める
ご家庭で練習していただくにあたり、お願いしていることがあります。それは、
練習の開始時刻を決めること
です。
他のおけいこ事やご家族、ごきょうだいのご都合もありますから、曜日によって時間が違うのは構いません(月曜日はスイミングのあと18時から、火曜日は何も予定がないから17時から、など)。
無理なく続けられるスケジュールをお子さんと話し合って決めていただき、ピアノの練習を生活の一部に組み込んでいく、これが大切です。
同じ声掛けをしていただくにしても、「ピアノの練習するよ~」より、「17時だから練習しよう!」と具体的に伝えた方が、より効果的だと思うんです。
ただこの習慣化、そんなにすんなり出来ないのもよくわかります。私も息子(小1)に学校の宿題をやらせようと、時間を決めて声掛けをしているのですが、まだまだスムーズに机に向かってはくれません(汗)。
でも学校の先生も、懇談会の度におっしゃっていました。「今のうちに勉強の習慣を身に付けさせてください。」と。「高学年になれば、だんだん宿題そのものも見せてくれなくなりますし、中学生になっていよいよ勉強が難しくなってから手伝おうにも、親御さんも急には答えられないと思いますよ。」
担任の先生のお話に、妙に納得してしまいました。ピアノも一緒ですね。
レッスンを始めたばかりの頃、一日の練習時間なんて5分か10分で済んでしまうような時から、できるだけ毎日ピアノに向かうように、声掛けをしていただきたいのです。
そうは言っても、お子さんの気分が乗らなかったり、他に予定があって、「3曲宿題になっているうち、今日は1曲しか練習できなかった…」という日もありますよね。そんな時は、次の日の練習量をほんの少し増やしたりして調整していきましょう。
回数を決める
もうひとつおススメしているのが、
○○分練習する、ではなく
○○回弾く、という方法です。
これは、まだ一曲が短い 小さなお子さんに特に有効だと思います。
私はよく生徒さんに「自分で『上手に弾けた!』と思うのが5回になるまで練習してね」という宿題を出します。○○分、という練習時間の長さを目安にするよりも、○○回という目標の方が、上手になっていく過程を実感できると思うんです。
勉強でも、新しく習った漢字を10回書くとか、計算プリントを1枚解くとか、時間で区切るより具体的な量を提示してあげた方が、ゴールが分かりやすいのでやる気も出ますよね。
私も振り返ってみれば、中学生くらいまでは、母に時間の管理をされていたなぁと思います。子どもですから、いくらピアノが好きでもサボりたい時もあれば、お友達と遊びたい時もあります。それでも「17時までには帰ってきなさい!」とか「この日は出掛ける予定があるから、朝ご飯が済んだら練習ね。」などと言われ、うるさく感じることも正直ありました。ですが、今となっては感謝しかありません。
私の生徒さん達も、時期はまちまちですが、いつの間にかお母様の手を離れ、自分なりにルールを決めて練習しているようです。それを実感したエピソードがありますので、最後にご紹介しますね。
いつの間にか自立していたT君
何でもそつなくこなすT君(中2)。小学生の頃からサッカーも続けていて、学業も優秀。中学生になり、ずいぶん口数は少なくなりましたが、ピアノも嫌々通っているわけではなく、宿題はキッチリこなしてきます。お母様も上手に声掛けをしてくださっているのだなぁと思っておりました。
発表会を翌週に控えたある日のレッスンに、お母様が久しぶりにお見えになった時のことです。
「先生、今回の発表会の曲、きのうやっと聴かせてもらえたんですよ!」
お母様の言葉にT君は苦笑い。私はあまりの驚きに、しばらく固まってしまいました。
どうやらT君、おうちのピアノのサイレント機能を使ったり、お母様がいらっしゃらない時間をねらったりして練習していたようなのです。
「先生からお電話いただくこともなかったので、なんとか練習出来ているのかなぁとは思ってましたけど…」とお母様。私の知らないうちに、ずいぶんと成長していたんですね。
T君の例も少々極端かもしれませんが、お子さん達は必ずいつか自立していきます。『今はとにかく手がかかって大変なんです…』というお母様に、この記事がヒントになれば嬉しいです♪
こちらもぜひご覧ください(^^)