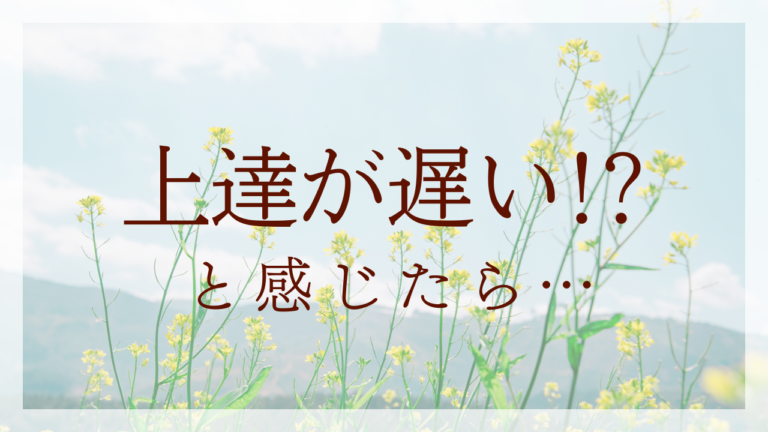他のお子さんとの差が…
こんにちは!入間市で子ども向けピアノ教室をしております、いいじまです。
お子さんをピアノ教室に通わせている親御さんに、こんなお悩みはありませんか?
「うちの子、上達が遅い…?」
私の息子(小1)は年長さんの時からスイミングスクールに通っています。が、まぁ亀の歩みで…^^;
小学校の同級生も、ちらほら同じスクールで見かけるのですが、みんな息子より上のクラス。
習い始めた時期が息子よりも早い子がほとんどなので、当然と言えば当然なのですが、それにしてもこの差は…と、ついつい他のお子さんと比べてしまうのが親心でしょうか。
ピアノでも、「Aちゃんね、もう○○(曲名)弾いてるんだって」というような話をお子さんから聞いたり、発表会で他のお子さんの演奏を聴いた時など、「うちの子、大丈夫かしら…?」とモヤモヤしてしまうお母様もいらっしゃるかもしれません。
先述のスイミングの話に戻りますが、練習を見ていると、息子はいつも同じことをコーチに指導されている様子。そのことを指摘すると、
「言われてることはわかるんだけどね、それがなかなか出来ないんだよ。」
息子の言葉に、思わずハッとさせられました。
そうですよね、頭で理解できたからと言って、すぐに体が反応するかどうかは、その子次第です。
その子なりの成長が必ずあります
ピアノのレッスンも一緒です。同じ年齢で同じテキストを使ってレッスンを始めたとしても、進み具合いはいろいろです。しばらくすると、お子さんのタイプも見えてきます。
例えば、
・指はよく回るけれど、表現力がイマイチ…(小さい頃の私はこのタイプでした^^;)
・テクニックが追いついていないけれど、表情のある演奏をする、などなど。
また、ひとつのことをマスターするのに、とても時間のかかるお子さんもいます。
ピアノは学校の勉強と違い、いつまでにこれをやる、というような明確なカリキュラムはありません。
生徒さんに合わせて、その都度考えながらレッスンしていくものです。
発表会の選曲にしてもそうです。出来るだけその子の”長所”が生きる曲を選ぶようにしていますが、長い期間かけて取り組むことになるので、あえて”イマイチ”な部分に挑戦してもらう時もあります。
ですから、他のお子さんと比べるのではなく、お子さん自身のがんばりを見てあげてください。
1か月前ではあまり変化がないかもしれませんが、1年前と比べたら、
・レパートリーが増えた
・譜読みが早くなった
・左右の音のバランスに気をつけられるようになってきた
・音の出し方が丁寧になってきた
などなど、きっと何かが良くなっているはずです。
こんなケースもありました。
遅咲きだったMちゃん、実はこんなセンスが⁉
私が楽器店のピアノ講師をしていた頃の話です(現在は自宅にてピアノ講師をしております)。
Mちゃんをお預かりすることになったのは、彼女が小学3年生の頃だったと思います。
それまでMちゃんは4年ほどグループレッスンに通っていたのですが、グループの先生曰く、「とにかくのんびり屋さんで、実はカリキュラムが消化しきれていないんです…」と。(グループは決まったテキストとカリキュラムに沿ってレッスンしています。)
確かに、4年間で目標とするレベルには達していませんでした。ただ、Mちゃん自身はそのことを全く気にする様子もなく、毎週ニコニコしながらレッスンにやってきます。
お母様とお話ししても、「おしりを叩いてはいるんですけどねぇ。」とおっしゃるものの、特段焦っている感じでもありませんでしたので、じっくりレッスンすることにしました。
やはり一番の問題は読譜力。はじめの頃はレッスン内でも読譜にかなりの時間を費やし、手がかかりました^^;
それでも音楽は好きだったのでしょう、中学で吹奏楽部に入ったMちゃん。フルートの担当になり、嬉しそうです。かなり熱心な部だと他の生徒から聞いていましたので、大丈夫かなぁ…?と心配しましたが、思いがけず良い効果が‼
毎日難しいリズムに取り組んでいるうち(吹奏楽って、ピアノより複雑なリズムがたくさん出てきます)、やっと彼女の頭の中で算数と楽譜がつながったようで、読譜力が格段にUPしたんです‼
ここから一気に演奏力も、と言いたいところですが、そこはマイペースなMちゃん。そんなに甘くはありませんでしたが、彼女なりの上達が見られるようになりました。
発表会ではMちゃんより年下の子が、よりレベルの高い曲を演奏したりもしましたが、相変わらず気にする様子はありません。発表会ともなると、ちょっとしたミスで落ち込んでしまう子もいます。また学年が上がるにつれて、ステージで演奏することに消極的になってしまう子も多い中、Mちゃんは違いました。
「自分の好きなことに、いつでも楽しく向き合える。これがMちゃんの長所なんだね♪」と、私もちょっと羨ましく思うほどでした。
部活動の方も充実した3年間だったようで、高校へは楽器推薦で進学。ますます忙しくなる中、ピアノのレッスンも休まず通ってきてくれました。
その後、私が楽器店を退職することとなり、Mちゃんとは高校2年生の終わりまでだったのですが、一年後、Mちゃんを引き継いでくださった先生から、
「Mちゃん、フルートで音大へ行くことになりました!」
との連絡が。あまりの衝撃に、「え⁉本当に⁇」と聞き返してしまいました。
高校生になってからフルートの個人レッスンにも通い始めた、という話は聞いていたのですが、まさか専門の道へ進むとは…!
いつもニコニコしていて擦れたところがなく、素直だったMちゃん。残念ながら彼女のフルートを聴く機会はありませんでしたが、きっと彼女のそんな性格が、音に表れていたのでしょう。
また、Mちゃんの性格を理解し、他の子と比べることなく、おおらかに見守り続けたお母様の存在も大きかったのだと思います。
レッスンを通して身に付く力
ピアノの練習は、”コツコツ”の積み重ねです。新しい曲をもらった時は、出来ないこと、弾けない箇所がたくさんあります。その課題に前向きに取り組むことで、少しずつ曲が形になっていきます。
すんなりクリアできる課題もありますが、なかなか乗り越えられないものもあるでしょう。でも途中で投げ出してしまったら、その曲は仕上がらないままです。
ですから私たち指導者は、「こんな風に弾いてみたら?」とか、「こんな練習方法があるよ。」などとアドバイスをするわけですが、私たちは手助けしか出来ません。課題を克服していくのは、生徒さん自身なのです。
自分ががんばることで課題をクリアし、一曲レパートリーが増えてまたピアノが楽しくなる。
このような経験を積み重ねていくことで、『コツコツと努力すること』や『あきらめずにやり抜く心』を身に付けていってほしい、そう願いながらレッスンしています。そして、そんなお子さんをいつも見守ってくださる保護者のみなさまのことも、心から応援しております♪
こちらもぜひご覧ください(^^)